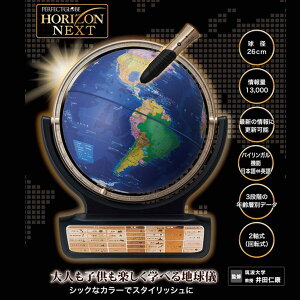リビングで勉強=まさかの東大入学?
皆さんこんにちは!GOLDHOME管理人です。
突然ですが皆さんは、子供をどこで勉強させていますか?
今日は「もし親御さんが子供を勉強させたいなら、リビングで勉強してもらうことをおすすめしたい」というお話しをしていきたいと思います。
では早速いきましょう!
学習机(勉強机)はいらない
さて子供が小学生になるかという時、親の悩みどころとして「子供の勉強場所をどうするか」というのがあります。
その時の選択肢としてポピュラーなのは、「学習机(勉強机)を買う」なのではないでしょうか?
ライフスタイルも多様化しているので一概には言えませんが、実は、「小学校入学時点で学習机(勉強机)は買わない方がいい」んです。
この事は今では、多くの人が耳にした事があると思います。
管理人はかな~り前に、テレビで見かけました。
まだ子供がいない頃です。ついでに言うと、彼氏もいませんでした(笑)。(←100年前かっ?)
その内容は当時衝撃的でしたが、とても納得のいくものでしたから、「自分の子供が生まれたら、必ずそうしよう!」と考えていました。
それは「勉強机ではなく、リビングで勉強した方が良い」「そうすれば東大生になれるかも」という情報でした。(←うろ覚え)
自分の子供が東大に入るなんて考えませんでしたが、なるほど、親にとっても、子供にとっても、メリットが多いんです。
なかば「ほんまかいな」と思いながら、「子供が生まれてくれた暁には、リビングで勉強させてみよう」と、ちょっと実験的な考えでそう決めていました。
まさか自分の子供を東大に入れようとか、そんなおこがましい考えはありませんよ、もちろん。
でも管理人の場合、確かに学習机(勉強机)は、あまり使っていた記憶がありませんね。(←単に勉強してない)
ちなみに管理人が勉強机を何に使っていたかというと、とにかく雑貨を飾ったり、物を置く場所として活用しておりました。(←自由人として生きていた。)
スポンサーリンク
値段の高い風水グッズや財布だけじゃない!プチプラ風水アイテムで運気上昇に効果的な方法5選!
なぜ学習机(勉強机)がいらないのか?
《学習机(勉強机)のメリット》
①子供が集中できそう。
②「買ってあげた」という親や祖父母の満足感。(←おい)
③学校の道具を全て収納できそう。
④後片付けがおろそかになっても、生活の邪魔になりにくい。
と、この辺が学習机を買うメリットなのだと思います。
「勉強専門の場所」の落とし穴
「勉強専門の場所」というのを確保すれば、なんか勉強したくなりそうですよね?
親は子供部屋を与えて学習机を揃える事で、親の役割の大半を完了した様な気がしてしまいます。
「勉強する場所を整えてあげた」
↓
「だから勉強するのが当たり前だろう」
といのうは親側の都合です。
個人的に、この親側の気持ちは100%わかります(笑)。
しかし!
実はここに大きな落とし穴があるのです。
「基本的に、多くの子供は勉強が好きじゃない」という落とし穴です。
例えば学習机じゃなくて、「レゴ机」とか、「バービー机」とか、何か子供の趣味に特化した机なら、子供は喜んで一日に何度も机に向かうかもしれません。
しかし、学習机は「そこに向かったが最期、勉強しなければいけない」のです!(←イヤ当たり前だが。)
言い換えると「さあ勉強するぞ!」という気持ちじゃないと
「子供が座りたくない場所なのだ」という事です。
結果、どんどん学習机に向かう時間が減ってきます。
学習机って、実は・・・・
「勉強と生活を完全に分けてしまう」アイテムなんですね。
でも本当は、分けない方がいいんです。
これは管理人の体験も交えてそう思うのですが、勉強する場所や時間を分けることで、
取り掛かりのハードルがとても上がってしまうからです。
掃除もそうですが、勉強も日常生活の流れの中でスッと取り掛かれる方が、
子供にも親にも負担がかかりません。

西キッチンの「色」と「風水インテリア」〜方角別・金運上昇のキッチン風水〜
「いじめられている子供に親がとれる対処方法」心理・行動・風水の合わせ技で子供を守る!
今まで幼児からの勉強のやり方を書いてきましたが、
子供が勉強を好きになるには、ハードルを限りなく低く設定する必要があるんです。
特に勉強の習慣が身につくまでは、
「日常生活と勉強が、自然に馴染んでいる」
のが一番良いのです。
「遊びと勉強を分けない」
「生活と勉強を分けない」
という生活様式に変えることこそが、実は最良の勉強方法となります。
子供時代の記憶がある方ならお分かり頂けるかもしれませんが、
急に「ハイここから勉強ね!」とうまく気持ちを切り替えなければできない事が、
子供を勉強を嫌いにさせる理由の一つなんですね。
これは掃除嫌いの大人にも、ほとんどの場合で当てはまります。(^^)
だから
「いちいち自分の部屋に行って、学習机に向かわないと勉強できない」
ではなく、いつも過ごしてるリビングでやる方がいいのです。
リビングでと書きましたが、ダイニングでもOKです。
「気構えなく取り掛かれる事で、勉強タイムに抵抗がなくなる」
という訳ですね。
掃除だって、リビングに居ながらにして掃除道具をすぐ出せれば、
思いついた時にサッと行動しやすくなります。
掃除を小まめにしない理由として、ほとんどの大人の理由は
「取り掛かるのが面倒だから」なんですね。
なので自分の過去のデータとも合致するのですが、
「掃除道具の出し入れがしにくい家庭→掃除回数が減る」
んです。
それと同じで、「別部屋に勉強専門の場所を整える」という方法は、
「子供の成績アップについては、非常に効率が悪い」
という訳です。
「勉強専用の場所を確保する事は、子供の勉強に対して
更にハードルを上げる可能性がある」というのを覚えておいてください。
まあ管理人はリビングに勉強机を置いてもらっていながら、全然勉強しませんでした。(←おい。)
忙しい親御さんにはとても酷なのですが、
親が勉強を見守るという姿勢でうまく誘導していかないと、
おそらくほとんどの子供さんは、勉強が嫌いになるパターンが多いと思います。
管理人の子供も、
管理人見守る→勉強ノリノリ
管理人が放置する→勉強しない
をかなりの数、いったりきたりしています。
学校以外の学びは好きで放置しても勝手にやるのですが、
とにかく学校の宿題が嫌いなんだそうです。とほほ。
リビングに勉強場所を置くだけではなく、やはりしっかりと見守る様にしてみましょう。
スポンサーリンク
金運アップに効く!!グングン金運が上がる方法/「旦那の仕事運・金運を上げる風水8選」
すぐそこに家族
リビングダイニングで勉強をする場合のメリットとして、お母さんや家族が傍にいるという事があります。
これは子供にとって、とても大きなメリットです。
わからない事があればすぐに聞く事ができますし、寂しくありません。
子供が勉強が嫌いになる原因の1位は、「わからない・進まない」という事です。
そこで作業が止まってしまい、なんだか面倒になってくるんです。
(←身に覚えがある。)
信頼できる大人が傍にいて、わからない時にすぐ教えてくれたら、そうそう嫌いになりません。
それに「お母さんが見てる」と思えば、子供は一人の時の何倍も、頑張る
事ができるんです!
↑(もちろんお母さんに限らず、お父さんでもおばあちゃんでもOKです。)
「すぐに問題を解決できる」
というのは、「子供が勉強を楽しめる最良の環境」になります。
何回も繰り返していると、きっとだんだんと一人で取り組む様になります。
アロマオイルおすすめ「ローズマリーの効能と効果」~若返りの妙薬?~
シナモンの効能効果がすごい!長年のかゆみから解放されました。〜管理人の体験談〜
すぐそこに辞書や教科書
リビングで勉強するという事は、
「すぐそこに何かを調べたりする道具が揃う」
という事になりますよね。
すると例えば家族でテレビを見ている時、漢字やら国の名前やら、色々な情報が出てくるんです。
家族の会話ひとつにしても、子供にはわからない単語だったりが出てきて、
何それ?
となる事があります。
その時に辞書があったり地図があったりすると、すぐに調べる事ができるんです。
知らない→すぐに調べる→わかった
これは、子供の頭を良くする最良の方法なんですね。

リビング風水(4)座るだけでぐんぐん運気が上がる!運気アップのソファ風水
子供が親に質問しなくなる時
子供って、親に色々質問をしてきますが、ある年齢でパタッとそれがなくなる時が来ます。
実はそれ、親のせいなんですよ。
↑悪い事ではないので、誤解しないでくださいね!
子供が、「リクエストに答えられない親に期待しなくなる」
というのが正解かもしれません。
ただ、それ自体は悪い事ではありません。
「子供の知識が広がったおかげ」で親が答えられないんですから、むしろ喜ぶべきです。

値段の高い風水グッズや財布だけじゃない!プチプラ風水アイテムで運気上昇に効果的な方法5選!
「気になる」→調べる→「ヨッシャわかった!」体験
「親が子供の質問に答えられなくなると、子供は親に質問しなくなる」と上で出てきましたが、
これは辞書や地図、教科書や大辞典をリビングに置く理由にもなるんですよ。
あ、パソコンなんかも良いですね。
何かを調べたい時に
「移動しなきゃいけないから面倒、や~めた!」
となれば、子供は調べるのをすぐに諦めてしまいます。
「気になる」→すぐ調べる→「ヨッシャわかった!」
↑この一連の流れさえストップしなければ、子供は自分が気になる事を、
「わかるまで調べる」というクセがつきます。
この「ヨッシャわかった!」までの流れは、子供の脳みそには最高のプレゼントです。
脳の「超・快感体験」なんですね。

「子供が勉強大好きになる方法」九九と漢字(幼児~低学年向け)
《答えが出ると「快感になる」瞬間》
昔テレビで「アハ体験」というのでやっていましたが、快感ホルモンが出て
いつの間にか「勉強=楽しい」になっちゃう訳です。
これうちの子供にも、本当にあてはまっています。
え~最近は、子供からの質問がほとんど来なくなって久しい管理人ですが(泣)、小さい頃はよく質問を浴びせかけられてました。
みんなそうだと思うんですが。
幸いにして(←おい)ママ友の少なかった管理人は、
子供の質問に対して、答える時間を充分にとる事ができました。
それで子供の「快感ホルモンが出た」んだと思います。
もともとおしゃべり大好きな管理人ですから、ママ友がたくさんいたら、
それこそ子供をほッぽりだして「ん~わかんない」とかテキトーに答えていた事でしょう。
辞書や大辞典で載っていない様な事は、パソコンに頼りました。
グーグルさんて便利ですよね、「スイレンの花の画像」って言うだけですぐ出てくるんですから。
基本的にはパソコンよりも、紙の情報の方が良いんです。
まだ研究途上ではありますが、電子画像は、記憶に残りにくいと言われています。
個人差もあると思いますが、管理人自身もその様な自覚がありますね。
(←いや君は脳の方が。)
金運アップに効く!!グングン金運が上がる方法/「理論編」~金運は2つある~
ティーツリーオイルの効能効果5選と体験談~知っておきたい副作用4つも解説~
「リビングで勉強」に一票入れます!
と、こんな訳で、管理人もリビングで勉強させる方が良いと思います。
「ヨッシャわかった!体験」の流れをつくる事で、東大レベルにまで到達する可能性は充分あるという事です。
ただし、間違えないで頂きたいのが、
もちろん親が子供の「何だコレ?」→「ヨッシャわかった!」までの
サポートをする必要がある
という事です。
リビングで勉強させていても、100%放置では子供は勉強好きになりませんから御注意を。
ちなみに管理人の生まれた家は、リビングの端に子供の人数分の学習机を並べていました。
当時はリビングの使い方を、周囲に不思議がられていましたね。
そんな家で過ごした一番上の兄弟は、勉強大好きと豪語し、かなりハイレベルな国立大を滑り止めとしていました。
でも同じ環境で育った管理人を含む他の兄弟は、そんなにハイレベルまで到達できませんでした。
たぶん理由は放置されていたから
だと思います。
一番上の子供の時は、親も必死であれこれ見守るんですが、
2人目からは「そんなに手をかけない子育て」に変わってしまったようですね。
やはり、「勉強の楽しさがわからなかったから」だと思います。
長男長女というのは、どちらにしても、こと教育に関しては兄弟の中で一番手厚い待遇を受ける事が多いんです。
良い悪いはどちらもありますが、こと学習に関しては、本当にそう思います。
初めての子供って、どうしたら良いか物凄く悩みますし色々考えます。
2番目からは親も安心してしまい、細かい所まで考えないんですよね。
ただ、
「親が教えていくかどうかで、これだけの差が出る事がある」
という事を、管理人自身の体験をお知らせする事で、皆さんには知っておいて頂けたらと思います。
子供が勉強好きだと、色々と教われて楽しいですよ!
(↑親の威厳=完全放棄)

子供が勉強しない!→簡単に「子供が勉強大好き」になる方法(小学生~中学生編)
《学習机は悪者ではない》
色々と書いてきましたが、学習机は全然悪くありません。
むしろ学習机をリビングに置くというのは、とても賛成です。
いつでも取り掛かれる状態にするのが一番良いので、片付けがそんなに細かく必要ない学習机を置いておくととても楽です。
ライフスタイルによっては、「リビングやダイニングの机を子供に占領されてしまうと困る」という場合もあるかと思います。
そんな時はリビングに学習机を置いたり、極力近い場所に勉強場所を設けたりできると良いですね。
管理人の家では、小さいうちはリビングテーブルで、途中からはリビングの端に学習机を置いて勉強用としています。
生活動線がとても便利で、気に入っています。
皆さんもぜひ、リビング学習を考えてみてください。
大人が勉強したい場合でも、とても便利ですよ。
オムニセブン(イトーヨーカドー・loft等の大手通販サイト)学習机 一覧へ
管理人がこの記事で伝えたいのは、「子供の成績をある一定のレベルに到達させたいなら、家族のサポートが必要不可欠である」という事です。
これは完全に体験したから、ぜひとも今悩んでるかもな誰かにお伝えしたいと思った次第です。
「学習机自体が悪いのではない」んです。
放置しても、ほとんどの子供は勉強しない
というだけですね。
子供には、
「孤独でも自分で勉強してもらおう」という親の願いは、ほぼ通用しない
という訳です。
家族のサポートは、はたから見ると簡単な事だと思われがちですが、
実はある時期までは、とても手間がかかります。
但し、手間が物凄くかかるのは、
子供が「勉強好きになり、自分で調べる」までの間だけです。
管理人の子供は小1の2学期からは、自分でほとんどの事を調べる様になりました。
その位になると、大体↓の3パターンで済んでしまいます。
手間の掛かった時期は、ざっとですが3年位なもんです。
その3年を乗り越えれば、後は基本的な応援のみで済みます。
もちろん応援は必要です。
例えばその後、高校生まで「勉強しなさい!」と尻を叩かなければいけない事と比べると、
かなりの労力や時間が節約でき、精神的苦痛(?)から解放される
という事がおわかり頂けるのではないでしょうか。
《子供が自分で解決方法を手に入れた後の親のサポート》
①「辞典や辞書でもわからない事を子供が聞いてくる→親にもわからなければ、一緒にネット等で調べる」
②「日常生活に支障をきたさない様に、親が介入して勉強を終わらせる」
③「いつも子供が楽しめる様に、成長を褒め称え、一緒に喜び、応援する」
これだけです。

管理人の子供は決して、特に元々頭が良い訳ではありません。
学校の成績がいつも良い訳でもありません。
「ただ勉強が好き」です。
YouTubeやら漫画やら本やら、とにかく多方面で知識を得る事に貪欲な感じです。
とにかく知的好奇心が旺盛です。
でもこれって、一番大事な事だと思うのです。
管理人は大人になってからわかったのですが、本来は人間にとって
学びは楽しい
ことなんですよね。
何か理由があって、つまらないものになってしまうんだと思います。
(↑子供の勉強をつまらなくさせた本人。)
子供に成績アップや勉強する事を求めるのなら、この方法が一番楽で手っ取り早いですし、親にも子供にもメリットがあります。
双方にメリット→「ウィン:ウィン」の関係は、勉強もビジネスも、対人関係も、全てにおいて一番効率が良いんですよね。
この記事の冒頭に有る様に、もし「子供が東大に行く」というのは一般的にすごい事ではあります。
しかし本来は「どんな学校に行くか」ではなく、
子供が「自分で勉強をする事を選ぶという事自体」が一番、子供にとっての重大なメリットになるのではないでしょうか。
勉強だけでは無く、子育てに悩みは尽きません。
管理人も様々な情報をテレビや本、ネットで手に入れ、思考錯誤の上で実験し(←子供ごめん)、やっと「勉強問題に限っては解放された」ところです。
たぶんまた他の問題が出てくることでしょう。
2020年、子供が突然勉強せずゲームにハマるという事態が発生し、
この記事を書きました。↓
まだまだ、落ち着く訳にはいかない様です。
もちろん子供がある程度大きくなってからも、たまにそばにいて他の作業をしています。
管理人はとても遠回りをしてしまったので、この記事が同じ様に「子供の勉強問題」で悩まれている皆さんのお役に立てたら、非常に嬉しいです。
それではまた!
人気のページ
「子供が勉強大好きになる方法」九九と漢字(幼児~低学年向け)
子供が勉強しない!→簡単に「子供が勉強大好き」になる方法(小学生~中学生編)
子供の風水~片付けも勉強も「子供が自分から」やりだす!!今スグできる!超簡単な方法~
スポンサーリンク